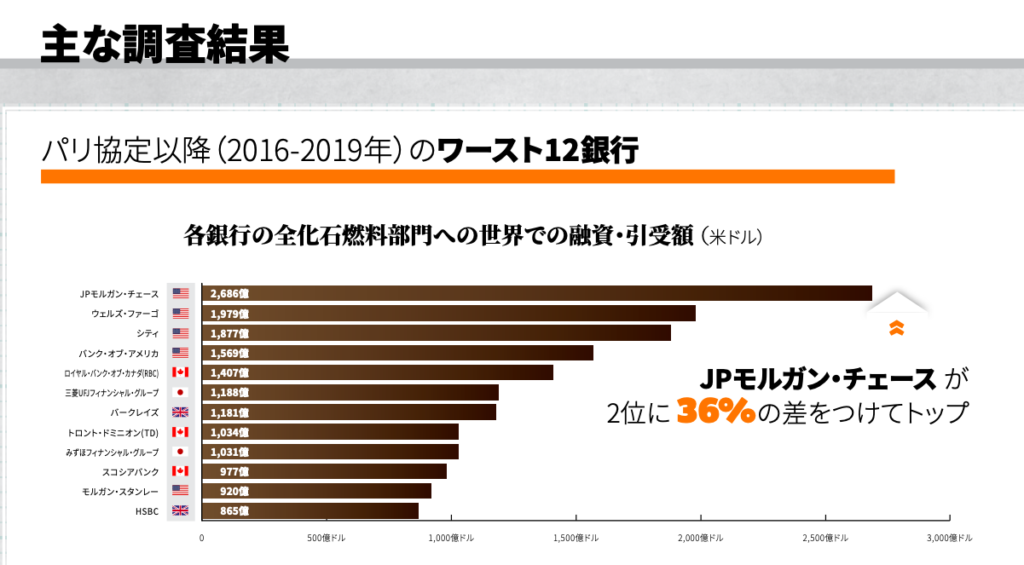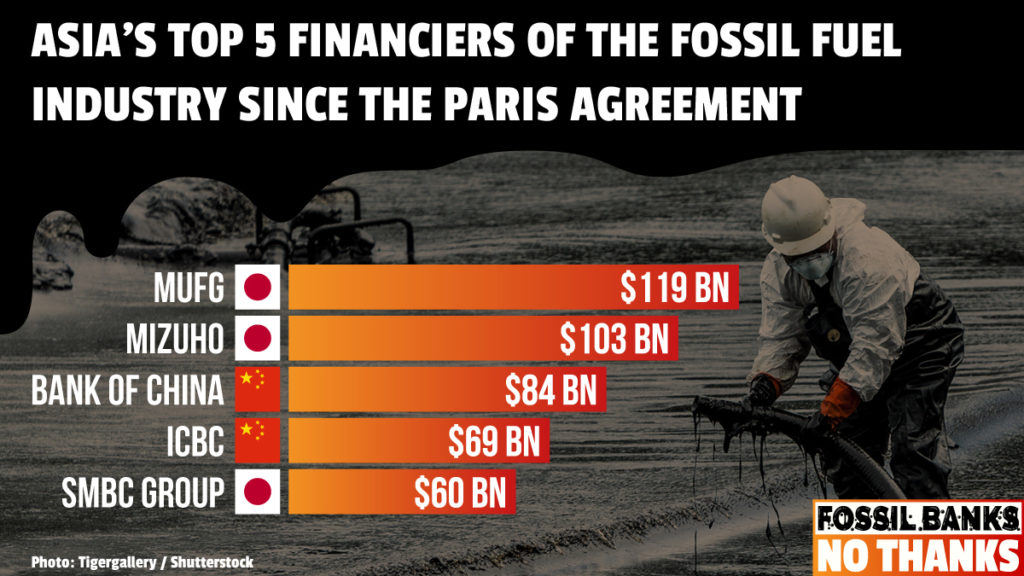NGO共同声明:東京五輪は「見せかけのサステナビリティ」(2020/3/30)
〜施設建設で東南アジアの熱帯林を破壊、調達の失敗から教訓を学び是正を〜
東京五輪および「持続可能性大会前報告書」公表延期を受けて
国内外のNGO8団体は、本日30日、東京五輪の延期を受けて、東京2020大会主催者に東京五輪の木材調達による環境および社会への悪影響を認めるよう求める共同声明を発表しました。東京2020組織委員会は持続可能性報告書を3回公表する予定でしたが、2021年までの大会延期によって、2回目の「持続可能性大会前報告書」も延期される見込みです。延期によって、組織委員会はこの報告書を見直し、調達の失敗と教訓を記録し、持続可能性の実現ための明確な道筋を示すことができます。

「本声明の賛同団体は、東京五輪も含め、世界中の人々が現在直面している新型コロナウィルスによる生命、健康、生計手段への深刻な影響による緊急事態を認識している。パンデミックおよびそれに付随する経済的影響への緊急対応が当面の優先事項とされるべきとの認識の下、今回の声明を発表している。しかしながら、地球が急激な気候変動と前例のない生物多様性の損失という二重の危機に直面していることには変わりない。私たちはこれらの危機について人々の意識が東京五輪によって高まり、地球に生きる私たちにとってより持続可能で公正な未来を実現できるよう願っている。
東京2020大会主催者は『持続可能な大会』の実施を約束しているが、現状は『見せかけのサステナビリティ』である。五輪施設建設に森林減少を引き起こした大量の熱帯材合板が使用されたことは明確な調達基準違反でありながら、基準の不遵守が起きていないように都合よく非常識な解釈をしている。前回の報告書(注1、2019年3月26日)では、大会主催者はこの問題に向き合わず、持続可能性の約束を守っているかのように見せかけようとしてきた。さらに、指摘された問題から学ぶという姿勢が見られない。このままでは東京五輪は『見せかけのサステナビリティ』でよいという『悪しきレガシー』を後世に残してしまう恐れがある。
大会開催が延期されたため、東京2020大会主催者は大会前報告書を見直し、持続可能性の面での失敗を認めて教訓とし、森林保護に必要な前向きな行動を促進できるはずだ。東京五輪が熱帯林破壊に加担した事実を認めて問題と向き合い、そして問題が起きた経緯を検証し、繰り返さないための対応策を教訓にすることが求められる。できたところだけを評価し、できなかった点は無かったことにしてしまうような、無責任な対応は許されない。持続可能性の担保方法に問題があった点を課題として真摯に認め、その是正策を国と東京都をはじめとする自治体、そして業界が持続可能な調達のために将来参考にできるよう、報告書で提示することが『真のレガシー』である。
森林、特に熱帯林は、地球の気候と降雨パターンを調節する重要な役割を果たしている。また、炭素を吸収かつ貯留し、そこに暮らす人々の生活や水、食料などの基本的ニーズを満たし、生物多様性の保護に不可欠である。森林と野生生物の生息地保護は、新型コロナウィルスのような死に至る感染症の防護物として認識され始めている(注2)。そのため、国連の「持続可能な開発目標」(SDGs)「ターゲット15.2」は2020年までの森林破壊阻止、「ターゲット15.5」は生物多様性損失の阻止及び2020年までに絶滅危惧種保護と絶滅防止の対策を講じることを目標としている。東京五輪はSDGsの推進も約束したが(注3)、熱帯材の大量使用はサステナビリティの取り組みと大きく逆行する。この点は、大会前報告書および大会後報告書に明記し、持続可能性に配慮した調達のための今後の教訓とすべきである」
賛同団体
レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN、米国)
TuK インドネシア(インドネシア)
サラワク・キャンペーン委員会(SCC、日本)
ウータン・森と生活を考える会(日本)
ブルーノマンサー基金 (スイス)
熱帯林行動ネットワーク(JATAN、日本)
国際NGO EIA(環境調査エージェンシー)
国際環境NGO FoE Japan(日本)
【これまでの経緯】
NGOは、東京五輪が熱帯林破壊に加担してきた問題を指摘し続けてきた。東京2020組織委員会が公表した情報によると(注4)、夢の島公園アーチェリー会場以外の全ての施設で熱帯合板が利用された。大会施設の基礎工事でコンクリートを成形するために使われた型枠合板は、インドネシアとマレーシア産合計で22万5千枚以上(全体の68%)にも上る。そのうち、持続可能性の認証を取得していないインドネシア産合板が新国立競技場と有明アリーナで、それぞれ約12万枚、約1万枚も使われた。国立競技場で使われたインドネシア産型枠合板は全体の36%を占め、丸太換算で約6,731立方メートルと推計される。これは、国立競技場の屋根等の国産木材使用量2,000立方メートルを上回る(注5)。また、認証されたマレーシア産木材の持続可能性も極めて疑わしい(注6)。以下、持続可能性の公約を守っていない二つの例を提示する。
持続可能でない「転換材」の使用について
第一に、持続可能でない「転換材」が大会施設の建設に使用された点にある。2018年5月、RANなどのNGOの調査によって、東京都が管轄する有明アリーナの建設現場でインドネシア産の型枠合板の使用が見つかった(注7)。この合板を製造した企業の工場では、2017年に製造された合板原料の約4割が炭鉱開発やアブラヤシ農園などの開発のために土地転換された熱帯林に由来していることが、インドネシア政府へ提出された書類によって確認された。その後、同インドネシア産合板を提供した住友林業は有明アリーナ及び新国立競技場の両方に転換材を提供したことを認め、東京都は有明アリーナに調達したインドネシア材のほとんどが転換材であったことを認めた。
このような「転換材」は森林を全面伐採する「皆伐」を伴うため、五輪の木材調達基準に定められた「中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林」由来とは言えない。また、科学者によると、すべての陸生種の約3分の2を熱帯林に生息しているといわれ、インドネシアは地球上の生物種の約1〜2割が生息する生物多様性の非常に豊かな国である(注8)。実際、五輪のために皆伐された熱帯林には原生林および絶滅危惧種のボルネオ・オランウータンの生息地の破壊も含まれることもNGOの調査でわかった。そのため、木材調達基準の「伐採に当たって、生態系の保全に配慮されていること」という項目にも反する(注9)。実際、五輪に皆伐された熱帯林には絶滅危惧種のボルネオ・オランウータンの生息地の破壊も含まれることもNGOの調査でわかった。
「通報受付窓口」の機能不全について
第二に、2件の苦情が上記の問題に基づいて大会主催者である東京都と日本スポーツ振興センターに通報されたが、苦情を受け入れず、責任逃れをするような姿勢も、持続可能性の約束を守っていない一例である。
2018年11月、RANは、ボルネオオランウータンと熱帯林を代弁して、新国立競技場を管轄する日本スポーツ振興センターと有明アリーナを管轄する東京都に、非認証のインドネシア産「転換材」の大量使用及びボルネオ・オランウータンの生息地を含む伐採地からの木材使用を理由に、調達基準の不遵守を通報した(注10)。しかし現在まで16カ月が経ってもこの通報については正式に苦情処理手続きを開始せず、東京都とスポーツ振興センターの対応には、これまでのやりとりで以下の4点の大きな疑問が判明している。
1.東京都の通報制度には、違反が疑わしい事例であれば対象案件とする規定があるが(注11)、不遵守が確定しなければ通報の処理手続きを開始しない、という独自解釈を行っている。
2.2019年1月の木材調達基準改定で「転換材」の調達禁止が追加されたが、東京都は改定前の「転換材」使用は、計画に基づいて農地などに転換され、適切に管理活用されるなら趣旨に反しないと容認されていると、重大な解釈変更を行っている。
3.東京都は、インドネシア政府によるオランウータン生息地評価では不十分で、オランウータンが伐採地にいることを証明できなければ不遵守とはならず、苦情として認めないとしている。
4. 日本スポーツ振興センターは、東京都が都への苦情を却下したという決定に基づき、同センターに通報された転換材の使用に関する苦情を却下した。
(*1〜3は、東京都との面談やメールでの返答、4は日本スポーツ振興センターからのメールでの返答による)
2019年3月に公表された持続可能性進捗報告書では「通報受付窓口」の運用が持続可能性を担保するメカニズムとして記載されたが、NGOの通報によって、このように通報制度が実際には機能していないことが明らかになった。
なお、上記を求めた署名には、世界中から約3万筆の賛同が集まっている。署名は二度にわたってオンラインで実施され、本日、組織委員会、日本スポーツ振興センター、東京都に提出された。同署名は、熱帯林破壊に関する通報を苦情処理の案件として受理すること、東京五輪の木材調達が熱帯林に与えた影響を調査すること、そして今後の調達方針の実施の改善について大会主催者に求めている(注12)。
注1)東京2020組織委員会「『持続可能性進捗状況報告書』の公表について」、2019年3月26日
注2)参考:英ガーディアン紙記事
「Coronavirus: ‘Nature is sending us a message’, says UN environment chief」2020年3月25日
「‘Tip of the iceberg’: is our destruction of nature responsible for Covid-19?」2020年3月18日
注3)国際連合広報センター「国際連合と東京2020組織委員会が東京2020大会を通したSDGsの推進協力に関する基本合意書に署名」、2018年11月14日
注4)東京2020組織委員会「『持続可能性に配慮した木材の調達基準』の実施状況に関するフォローアップについて」、2020年1月10日(2019年11月末時点。総数は33万1,700枚。その内、国産材は3万9,500枚、再利用は6万6,600枚でその多くは熱帯材である)
注5)注4)の公開情報によると、新国立競技場では117,800枚のインドネシア産コンクリート型枠合板が使われた。日本では、コンクリート型枠合板の典型的なサイズは、12X900X1800mm〜15x910x1820mmであり、合板の量を生産において利用する丸太の量に変換する場合に使用される係数は2.3となる(出所: UNECE/FAO)。これは約6,731立方メートルもの丸太材に相当する。
日本スポーツ振興センター「新しい国立競技場の竣工について」、2019年11月29日
※国立競技場で使われた国産材の少なくとも約9割が集成材であった。そのため、集成材における丸太換算率60%を適用すると(出所:林野庁)、約3,333立方メートルの丸太に相当する。
注6)RAN他「2020 年東京五輪熱帯材使用に関する公式な情報開示に対する NGO 解説」、 2018年2月
注7)RAN他、報告書「守られなかった約束」、2018年11月
注8)国際熱帯木材機関「熱帯林の生物多様性保全のためのITTO/CBD共同イニシアティブ」
ODA見える化サイト「生物多様性保全センター整備計画」
注9)東京2020組織委員会「持続可能性に配慮した木材の調達基準」(2019年1月改定)
※改定で「森林の農地等への転換に由来するものでないこと」が明記されたが、改定前の基準でも「中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するもの」と「森林に由来する」との記載があり、森林ではなくなる「転換材」は基準を満たせなかった。特に非認証材については「当該木材が生産される森林について、森林経営計画等の認定を受けている、 あるいは、森林所有者等による独自の計画等に基づき管理経営されているこ とを確認する」と管理経営されている森林についての中長期的な計画の確認が求められている。
注10)参考:RANブログ「東京五輪の木材スキャンダル、持続可能性と説明責任に問題あり」2019年9月9日
注11) 東京都「『持続可能性に配慮した調達コード』に係る通報受付窓口 業務運用基準」
注12)RANは東京2020大会主催者宛て(東京2020組織委員会、日本スポーツ振興センター、東京都)に、2回の署名を実施した。
2019年11月の署名(英語)
2020年3月11日の署名(英語)
レインフォレスト・アクション・ネットワーク
本件に関するお問い合わせ
広報 関本 Email: yuki.sekimoto@ran.org