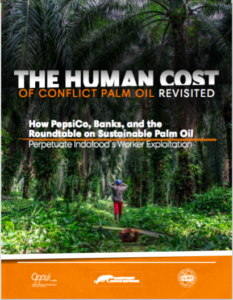お知らせ:APP社「森林保護方針」5周年について(2018/2/6)
レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)は2月6日、APP社(アジア・パルプ・アンド・ペーパー)が「森林保護方針」を2013年2月に発表してから5年が経過したことを受けて、下記を発表しました。
「森林保護方針」5周年となるAPP社の現状について、業界の方々へのお知らせ
インドネシア最大の紙パルプ会社、APP社(アジア・パルプ・アンド・ペーパー)は、2013年2月、“革新的”な「森林保護方針」(FCP)を新たに発表し、製紙原料生産のための天然熱帯林伐採を停止すること、また人権を尊重し、自社植林地の拡大が引き起こした数多くの地域コミュニティとの土地紛争に対処することを誓約しました。それから5年が経ち、一部では明らかな進展が見られました。しかし、APP社とその関連会社にはまだ長い道のりが残されています。泥炭火災や人権侵害など、深刻な環境・社会問題を未だに起こしています。さらに、透明性と説明責任の問題や、森林保護方針の実施速度と有効性は、依然として問題になっています。
これらの問題は、AP通信による先般の調査で浮き彫りになりました。その調査では、シナルマス・グループ(SMG)と同グループの紙パルプ事業を担うAPP社が、国内外の複雑な企業体制やその他の手法により、数多くの事業管理地を秘密裏にコントロールしていたことが明らかになりました。これらの事業管理地は、スマトラ島にあるAPP社の巨大なOKIパルプ新工場や他工場へ、現在、または将来的に原料を供給する可能性があります。SMG/APP社が秘密裏にコントロールしている事業管理地では天然林の伐採が疑われるほか、APP社が新たに木材サプライヤーとして加えようとしている企業の事業管理地では地域コミュニティから「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意」(FPIC)を得られていないなどの問題があります。
SMG/APP社は、サプライヤー企業やサプライヤー候補企業は同社から分離していてコントロールはしていないと主張していますが、この主張が虚偽であることをAP通信の記事は示唆しています。これまでSMG/APP社は、この主張を様々な場面で都合よく利用してきました。シンガポール政府などには2015年に起きた壊滅的な火災の幾つかに対する責任を否定し、顧客や政府などには同社事業による社会的及び環境的影響の内容や程度を欺き、独立認証機関には改革努力の実施や業務改善を確認するための検証作業の範囲や内容についても誠実さを欠いた交渉だったのです。
またAP通信の記事では、SMG/APP社が投資家、株主、政府、一般の人々へ公開しているほとんどの重要な情報について、その内容と正確性を疑問視しています。記事で明らかになった新事実により、隠された関係の最終的な受益者について疑念が出てきており、規制や税制上での予期せぬ影響を及ぼす可能性があります。
SMG/APP社は、投資家、顧客、政府などから過去数年にわたって、また最近では関係再開を模索している森林管理協議会(FSC)から信用を取り戻そうと試みています。しかし、サプライヤー企業やサプライヤー候補企業とのつながりや管理についての誤解を招くような説明は、そのSMG/APP社の信用を損なってしまいます。
以下、AP通信の調査によって明らかになった2つの事例を考察します。
一つ目は、ボルネオのムアラ・スンガイ・ランダック(Muara Sungai Landak)社に関連する事例です。同社は、シナルマス社の従業員2名によって所有されています。AP通信は「(SMG/APP社が)森林伐採を停止するという誓約に間接的に違反している証拠」を、「ドローン写真と衛星画像から」、そして「熱帯林を伐採する際に支払う賦課金を追跡する政府記録から」発見し、2014年以降、著しい森林破壊が行われていることを明らかにしました。
二つ目は、バングン・リンバ・セジャテラ社(Bangun Rimba Sejahtera、BRS)の事例です。同社は、2013年に南スマトラ沖の小島、バンカ・ブリトゥン島にパルプ材用の産業植林地を開発する許可を得ました。BRS社はSMG/APP社から独立しているとされていますが、 実際はSMG/APP社によって設立されたようです。AP通信によると、同社は「2007年には、マルガレータ・ウィジャヤ(Margaretha Widjaya)氏によって所有されていた。同氏は、2002年から2008年にかけてシナルマス・フォレストリー社(Sinarmas Forestry)の副社長を務めており、また、SMG創業者の孫娘でもある。企業記録によると、BRS社は数年にわたって2層の持ち株会社に所有されており、これらの持ち株会社の住所には、シナルマス社の複数の事務所が登録されていた。また、企業のトップと株主にはシナルマス社の幹部が含まれていた」と報道されています。
BRS社が取得した事業管理地は、地域コミュニティが伝統的に所有してきた土地です。同社による管理は、地域コミュニティによって広範に反対されていて、わずか数週間前の2018年1月19日には、数千人もの地元住民が州知事事務所の前で集会を行い、BRS社の管理許可をインドネシア環境林業省が取り消すように要求することを知事に求めました。
BRS社の事例は、APP社がOKI工場に木材を調達するために供給源を拡大した最初のケースで、SMG/APP社とBRS社の関係についての虚偽に加え、影響を受けるであろう数多くの住民からは管理許可とパルプ材用植林計画についてFPICが得られていないことが明らかになっています。BRS社の管理に対する地域コミュニティと地元政府の反対を考慮しなかったことは、APP社が持続可能性についての誓約に反したということであり、また、法的義務にも違反した可能性があります。 昨年3月、BRS社に対する地域コミュニティの抗議に関して、インドネシアNGOと国際NGOの60団体が懸念を表明し、書簡をAPP社へ提出しました。しかし、APP社からの回答はないままです。
AP通信の調査結果は、森林破壊や地域コミュニティの権利侵害のみならず、巨大OKI工場の原料調達元を拡大するためにSMG/APP社が行っているその他の問題行為という高いリスクがあることを、紙の購入企業や投資家などに示しています。これは、投資家、購入企業、政府、認証機関、地域コミュニティへの警鐘です。
SMG/APP社は、これまで刑事告発、市場からの圧力、FSCからの絶縁措置という結果をもたらしてきた行為や被害を再び繰り返すのでしょうか? SMG/APP社の約束は信頼に値するのでしょうか? AP社の記事は、SMG/APP社のガバナンスに関する組織的な幅広い問題を示しています。これらの問題は、SMG/APP社を信頼して取引を始める前に対処されなければなりません。
私たちは、紙の購入企業、投資家などに対して、以下を要請するよう求めます:
・AP通信の調査結果について、独立した調査を完了すること。調査では、合法性、税制上の影響、受益者の全面開示、APP社の利害関係者が参加する合意形成のプロセスでの誤解を招く説明について検討することを含み、また、調査にはインドネシア政府も関与すること。
・SMG/APP社は、BRS社及びその他の事業管理地において、地域コミュニティのFPICの権利を尊重すること。この権利には、地域コミュニティの土地でパルプ材用植林地開発を拒否する権利も含むこと。また、SMG/APP社は、BRS社をサプライヤーとして認めず、BRS社を管理許可と事業管理地から撤退させること。
・SMG/APP社は、APP社の事業により影響を受けるすべての地域コミュニティの情報を公開すること。これには、APP社が解決済みであると主張する紛争に関わる地域コミュニティの情報も含むこと。
・SMG/APP社は、原料を供給しているサプライヤー企業とのつながりと関係性を全面開示すること。また、産業植林地事業権(HTI)を保有し、現時点ではAPP社の工場に木材や繊維を供給していなくても将来は供給する可能性があり、同社の元従業員や現在の従業員、その他提携先と関連がある企業とのつながりや関係性を全面開示すること。
レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)